第1章:出会いと、不純な動機
退屈な座学研修がようやく終わった。
新卒でこの求人広告の会社に入社して4日間、ひたすらビジネスマナーや業界知識を頭に詰め込むだけの時間は、正直苦痛でしかなかった。明日からはいよいよ現場でのOJTが始まる。社会人としての本当のスタートラインに、俺は期待と少しの不安を抱えていた。
そして、運命の金曜日がやってきた。
「今日から君たち3人には、指導員の先輩についてもらう」
朝礼後、部長からそう告げられ、俺たち新卒3人は緊張した面持ちで顔を見合わせた。同期は、俺と、人の良さそうな佐藤、そして快活な雰囲気の鈴木だ。男2人、女1人の構成。一体どんな先輩が来るんだろうか。鬼のように厳しい人か、それとも――。
「紹介する。2年目の、高梨さんだ」
部長に促されて入ってきた女性を見て、俺は息を呑んだ。
すらりとした長身に、きゅっと引き締まったウエスト。タイトスカートから伸びる脚は、まるでモデルのようだ。艶のある黒髪を一つにまとめ、涼しげな目元が知的な印象を与えている。とても1つしか歳が違わないとは思えない、圧倒的に大人びた、非の打ちどころのない美人だった。
「今年から皆さんを指導させていただく、高梨美咲です。分からないことだらけだと思うけど、遠慮なく何でも聞いてください。一緒に頑張りましょう」
凛とした声と、ふわりと微笑んだ時にだけ見せる柔らかい表情のギャップに、俺の心臓は一瞬で鷲掴みにされた。
「さて、じゃあ早速だけど、今後の動きについて説明するわね」
高梨先輩は、俺たち3人を会議室に集めると、てきぱきと説明を始めた。
俺たちの仕事は、求人広告を出してくれる企業を見つけるための営業。その第一歩は、リストにある企業へ片っ端から電話をかけ、商談のアポイントを取り付けること、いわゆるテレアポだ。
「基本的な流れとして、まずは皆でテレアポをしてもらいます。そして…」
先輩はそこで一旦言葉を区切り、俺たちを順に見回した。
「アポイントが取れた人には、私が同行して、実際の営業の現場を見せてあげる。つまり…」
つまり?
「アポが取れた分だけ、私と二人きりで外回りをする時間が増えるってこと。逆に、取れなければずっと社内で電話番ね」
その言葉を聞いた瞬間、俺の頭に電流が走った。
(先輩と、二人きり…?)
隣の佐藤や鈴木も「頑張ろうな」なんて顔を見合わせているが、俺の動機は彼らとは明らかに違っていた。
営業成績を上げたい?もちろんそうだ。だがそれ以上に、この美しい先輩を独り占めできる時間が手に入る。あの知的な横顔を隣で眺め、良い香りを間近で感じながら、一緒に街を歩ける。
考えただけで、体の奥が疼くような興奮が湧き上がってきた。
「それじゃ、早速始めてみようか。誰が一番に、私を外に連れ出してくれるか楽しみにしてるわね?」
悪戯っぽく微笑む高梨先輩。
その笑顔は、俺の不純な闘争心に、静かに、だが確実に火をつけた。
他の二人になんて、絶対に負けられない。
何としても今日中にアポを取って、俺が一番に先輩を独り占めしてやる。
俺は固く、そう誓った。
第2章:二人きりの焼き鳥屋
「よーし、絶対一番にアポ取ってやる…!」
俺は誰よりも早く受話器を握り、リストの上から順に電話をかけ始めた。
横目でちらりと窺うと、高梨先輩は自分のデスクで淡々と仕事をこなしている。時折、こちらの様子を気にするように視線を送ってくるが、その度に俺は背筋を伸ばし、より一層電話に集中するフリをした。
先輩と二人きりの外回り。その甘美な響きだけが、俺の原動力だった。
しかし、現実は甘くない。
「申し訳ありませんが、今は結構です」
「担当者は席を外しております」
「今後、このようなお電話はご遠慮ください」
受話器の向こうから聞こえてくるのは、冷たい拒絶の言葉ばかり。何十件とかけても、アポイントどころか、担当者に繋がることすらままならない。午前中が終わり、昼休みを挟んで午後の部が始まっても、状況は一向に好転しなかった。
隣の佐藤や鈴木も苦戦しているようだったが、彼らの表情には「まあ初日だしな」という諦めにも似た色が浮かんでいる。だが、俺は違った。不純な動機で燃え上がっていた分、その落胆は計り知れないほど大きかった。
そして無情にも、定時を告げるチャイムが鳴り響く。
結果は、3人揃ってアポゼロ。惨敗だった。
「はい、お疲れ様。初日から大変だったわね」
終礼で、高梨先輩は俺たちの頑張りを労ってくれた。その優しい言葉が、今の俺にはかえって辛い。
「最初はみんなそんなものよ。今日の反省を活かして、また来週頑張りましょう」
そう言って微笑む先輩は、やはりどこまでも美しく、大人だった。
他の二人が「お疲れ様でした!」と元気に帰っていく中、俺は重い足取りで会社のビルを出た。空はすでにオレンジ色に染まり始めている。
しょんぼりと肩を落として駅へ向かう。結局、先輩と二人きりになるという下心は、脆くも崩れ去った。情けないやら、悔しいやらで、溜め息しか出てこない。
「…お疲れ。そんなに落ち込まないの」
不意に背後から声をかけられ、振り返ると、そこには高梨先輩がいた。俺に合わせて、歩く速度を緩めてくれたらしい。
「あ、お疲れ様です…」
「顔、死んでるわよ」
くすりと笑われ、俺はますます惨めな気持ちになる。
「いや、なんか、すみません。不甲斐なくて…」
「いいって。期待してたのは本当だけど、そんな簡単に取れたら誰も苦労しないわよ」
慰めてくれる先輩の優しさに、ほんの少しだけ気持ちが浮上する。だが、このまま別れて家に帰るだけでは、今日のこのモヤモヤは到底晴れそうにない。
「……酒でも、飲んで帰ります」
ほとんど無意識に、そんな言葉が口からこぼれた。
すると先輩は、呆れたような、でもどこか心配そうな顔で俺を見つめた。
「落ち込んで飲みすぎるなよ?」
その言葉に、俺の中の何かが弾けた。今しかない。このチャンスを逃したら、次はないかもしれない。
「――なら、見張っててください」
我ながら、大胆すぎる一言だったと思う。新卒の、しかも入社して一週間も経っていない後輩が、指導員の先輩を飲みに誘うなんて。
先輩は一瞬、きょとんとした顔で目を丸くしたが、やがて、ふっと息を吐いて悪戯っぽく笑った。
「しょうがないわね。一杯だけ付き合ってあげる」
「え…」
「いいよ」
信じられない言葉に、俺の心臓が大きく跳ねた。
こうして俺は、思いがけず、憧れの先輩と二人きりで飲むことになったのだ。
第3章:不意に見せた隙
先輩の意外な快諾に、俺の心臓は破裂しそうなくらい高鳴っていた。
駅前の喧騒を抜け、少し路地に入ったところにある、昔ながらの焼き鳥屋。赤提灯の温かい光が、仕事終わりのサラリーマンたちを吸い込んでいく。
「こういうお店、好きなんだ」
高梨先輩はそう言って、慣れた様子で暖簾をくぐった。店内は香ばしい煙と活気に満ちている。運良く、カウンター席が二つだけ横並びで空いていた。
「ラッキーだったわね」
そう言って俺の隣に腰を下ろす先輩。カウンター席だ。必然的に、その距離は近くなる。腕を動かせば、すぐにでも触れ合ってしまいそうだ。緊張で喉がカラカラになった。
「さてと…」
席に着くと、先輩は窮屈そうにしていたジャケットを脱いだ。すると、白いブラウスに包まれた、しなやかな体のラインがあらわになる。分かってはいたが、きゅっと引き締まったくびれと、そこから広がる女性らしい丸み。スーツ姿でも際立っていたスタイルの良さが、より一層強調されて見えた。
(うわ…スタイル良すぎだろ…)
思わず見惚れていると、先輩がこちらに気づいて「ん?」と首を傾げる。
「いえ、なんでもないです!」
慌てて目を逸らし、自分もジャケットを脱いだ。涼しいとはいえ、一日中歩き回ったり、慣れないテレアポで変な汗をかいたりもした。それなのに、ふわりと隣から漂ってくるのは、汗の匂いどころか、シャンプーのような、清潔で甘い香り。どうしてこの人は、こんなにも完璧なんだろうか。
「んー、まずはビールかな。君も飲むでしょ?」
「あ、はい!もちろんです」
ぎこちなく返事をしながら、俺は目の前のメニューに視線を落とす。だが、その内容は全く頭に入ってこない。意識はすべて、隣にいる先輩に集中していた。
「あ、ちょっと待って」
ビールを注文した後、先輩は「髪、邪魔だな」と呟き、まとめていた髪を一度ほどいた。そして、再び結びなおそうと両腕を上げる。その瞬間、俺の視線は彼女のうなじに釘付けになった。
その時だった。
「おっと、すまねぇ!」
ガタン、と大きな音を立てて、俺たちの後ろを通りかかった酔っ払いのおじさんが、大きくよろけた。そして、その手は――あろうことか、髪を結び上げようと無防備になっていた先輩の腰のあたりに、どん、とつかれた。
「ひゃっ…!」
先輩の口から、今まで聞いたこともないような、小さく甲高い悲鳴が漏れた。びくりと体を震わせ、その場に崩れ落ちそうになるのを、カウンターに手をついて必死に堪えている。
おじさんは「悪い悪い」と片手を上げて、そのまま千鳥足で去っていく。一瞬の出来事だった。
先輩はというと、髪を結うために上げていた手をおろし、よろよろと体勢を立て直している。結局、髪を結ぶのは失敗してしまったようだ。顔は少し赤く、目には生理的な涙が浮かんでいる。
「だ、大丈夫ですか!?怪我とか…」
俺が慌てて声をかけると、先輩はふるふると首を横に振った。
「ううん、大丈夫。ただ…くすぐったくて…」
そう言ってはにかむ先輩。いつもは完璧で、大人びて見える彼女が不意に見せた、あまりにも無防備で、可愛らしい姿。俺の胸の奥で、何かが「カチリ」と音を立てて切り替わったのが、自分でもはっきりと分かった。
第4章:完璧な先輩の弱点
「そうだったんですね…」
俺は安堵の息をつきながらも、頭の中は先ほどの光景でいっぱいだった。
(くすぐったい…?)
いつも冷静で、何事にも動じないように見える先輩の、意外すぎる弱点。そして、あの可愛らしい悲鳴と、潤んだ瞳。さっきまで落ち込んでいたことなんてすっかり忘れ、俺の心は別の種類の熱を帯び始めていた。
「もう一回、結びなおそっと」
先輩は気を取り直したように言うと、再び両腕を持ち上げた。
白いブラウスの袖がわずかにまくり上がり、きめ細やかな腕が伸びる。そして、豊かな黒髪がかき上げられると、先ほどよりも鮮明に、形の良い白いうなじがあらわになった。
ゴクリ、と喉が鳴る。
普段は決して見ることのできない、無防備な場所。そこから首筋にかけての滑らかな曲線は、妙に艶めかしく、俺の視線を奪って離さない。
(やばい…なんか、すごい…)
ドキドキと早鐘を打つ心臓を抑えきれない。さっきのおじさんの手が触れたのは、腰のあたり。髪を結ぶために腕を上げると、脇腹は完全にガラ空きになる。
もし、あそこに俺が触れたら?
(いや、ダメだろ。セクハラだ)
理性では分かっている。分かっているのに、指先がむずむずと疼くのを止められない。
さっきの「ひゃっ…!」という声が、耳の奥で何度もリフレインする。あの完璧な先輩が、俺の手で乱れたら、一体どんな顔をするんだろう。
衝動は、理性に勝った。
俺は、すぐそばに置かれていた注文用のタブレットに手を伸ばすフリをした。ごく自然な動きを装い、右腕を先輩の方へと滑らせる。そして――。
ツンッ
伸ばした人差し指の先が、先輩の柔らかそうな脇腹を、ほんの少しだけつついた。
「ひゃあっ!?ぁ、ははははっ!」
びくんっ!と、先輩の体が猫のように跳ね上がる。腕を上げたままの体勢を崩し、その場にうずくまるようにして、甲高い笑い声を上げた。
「ちょっ…!な、なにすんのよっ!」
必死に俺の手から逃れようと身をよじるが、カウンター席では動きが限られる。先輩は涙目で俺を睨みつけるが、その顔は怒っているというより、完全に笑ってしまっている。
「っ、はは、ごめんなさい!いや、なんか、無防備だったんで…」
俺もつられて笑ってしまう。
しっかり者で、いつも綺麗な澄まし顔をしている先輩が、こんな風にくしゃくしゃの笑顔で笑い転げている。その姿は、想像していたよりも何倍も、何百倍も可愛くて、俺の心臓を鷲掴みにした。
「もー…信じられない…」
ようやく笑いの発作が収まったのか、ぜぇぜぇと肩で息をしながら、先輩は潤んだ瞳で俺を軽く睨んだ。頬はほんのりと赤く染まっている。
「本当に、ダメなんだから…」
そう言って拗ねたように唇を尖らせる先輩。そのギャップに、俺はもう完全にノックアウトされていた。
第5章:警戒と油断、そして約束
「もう…結べないから、本当にダメだからね?」
ぷくっと頬を膨らませ、上目遣いで俺を睨む高梨先輩。その表情は、怒っているというよりも、じゃれている猫のようで、俺の庇護欲と、もっといじめたいというサディスティックな欲求を同時に掻き立てる。
「はいはい、分かりましたって」
俺が降参のポーズをとると、先輩はまだ半信半疑といった顔つきで、恐る恐る、といった様子で再び髪を結びなおそうと腕を上げた。その動きはさっきまでとは違い、明らかに俺の手を警戒しているのが見て取れる。
(そんなに警戒しなくても…)
その様子が面白くなった俺は、注文用のタブレットに手を伸ばしてみた。
「ひゃっ!」
俺が腕を動かしただけで、先輩は短い悲鳴を上げてびくりと体を震わせ、せっかく持ち上げた腕を慌てておろしてしまった。脇腹をがっちりとガードするその姿は、まるで小動物のようだ。
「あはは、警戒しすぎですよ、先輩。注文しようとしただけですって」
「う…、だって…」
「しませんよ、もう」
正直に言えば、もう一度、あの無防備な脇腹をつついて、可愛らしい反応をさせたかった。だが、さすがにやりすぎは禁物だ。俺は本心からそう言ったつもりだった。
俺の言葉に少し安心したのか、先輩ははぁ、と息をついてガードを解いた。
「あはは…。ほんと、昔からくすぐりだけは弱くってさ。自分でも嫌になるくらい」
照れくさそうに頭をかく先輩。その仕草が、またとてつもなく可愛い。
(くすぐりが弱い、か…。なんだよそれ、可愛いな)
完璧に見えた先輩の、人間らしい、そしてあまりにも無防備な弱点。それを知ってしまったことで、俺の中で彼女への感情は、単なる憧れから、もっと独占欲の混じった、生々しいものへと変わりつつあった。
その証拠に、俺がもう何もしないと信じ込んだのか、先輩もすっかり油断したらしい。ビールを一口飲み、焼き鳥を頬張りながら仕事の話をしているうちに、すっかりリラックスした表情になっていた。そして、三度目の正直とばかりに、今度は何の警戒もなく、すっと両腕を上げて髪をまとめ始めた。
がら空きだ。
白いブラウスの生地がぴんと張り、くびれから脇にかけての滑らかなラインが惜しげもなく晒されている。
もうダメだった。
触りたい。あの柔らかそうな場所を、この指で、もう一度。
俺は努めて冷静を装い、視線を手元のタブレットに落とす。メニューを選ぶフリをしながら、もう片方の手を、ゆっくりと、音を立てないように先輩の方へと伸ばしていく。
そして、
ツンッ。
指先が、再びその無防備な領域に触れた。

「きゃあっ!?」
今度は不意を突かれた分、さっきよりも素に近い、甲高い声が店内に響いた。
先輩の体は感電したかのようにびくんと跳ね、結び終えたばかりの髪がまたぱらりと肩に散らばる。
「こら!先輩で遊ばないの!」
真っ赤な顔で振り返り、潤んだ瞳で俺を睨みつける。その口調は怒っているのに、口元は照れと可笑しさで緩んでしまっている。楽しそうに、はにかみながら笑うその表情に、俺の心臓は完全に撃ち抜かれた。
「はい、すみません。もうしませんから」
俺はそう言って笑い、今度こそ大人しくタブレットを操作した。
そこからは、和やかな雰囲気で食事が進んだ。仕事のことからプライベートなことまで、普段は聞けないような話をたくさんした。アルコールも手伝って、俺たちの間の壁は、急速になくなっていくのを感じた。
酔いが回ってきたのか、先輩の表情がとろんとしてきた頃だった。
「…そういえばさ」
先輩が、ぽつりと呟いた。
「君たち新卒の成績って、実は私たちの給料にもちょっとだけ反映されるようになってるんだよね、今年から」
「え、そうなんですか?」
「うん。だから、頑張ってくれると、私も嬉しい、かな…なんて」
そこまで言って、先輩はハッと我に返ったように口を押さえた。
「あ、やば。これ、まだ内緒だったんだ。忘れて!気にしなくていいからね!?」
慌てて首を横に振る先輩。その仕草がまた可愛い。
だが、俺の頭には、ある悪魔的な考えが閃いていた。
「へぇー…。そうなんですね」
俺はにやりと口角を上げて、先輩の顔を覗き込んだ。
「じゃあ、俺、頑張りますよ」
「え、ほんと?よろしくね!」
「ただし、条件があります」
「条件?」
不思議そうに小首を傾げる先輩に、俺は満面の笑みで告げた。
「俺が契約取れたら、くすぐらせてください」
瞬間、先輩の顔から笑顔が消え、さーっと青ざめていくのが分かった。
「………だめ」
「えーーーーー。じゃあ頑張れません」
「なっ…!なにその理屈!」
駄々をこねる俺に、先輩は本気で困った顔をしている。その反応が面白くて、俺はさらに畳み掛けた。
「じゃあ、逆に、俺が契約取れたら、先輩をくすぐっていいって約束してくれたら、死ぬ気で頑張ります」
「う…」
先輩はしばらく腕を組んでうーん、とうなっていたが、やがて、諦めたように、そして俺を指差しながら、こう言った。
「………分かったわよ!その代わり、本当に契約取れたらだからね!取れなかったら、金輪際私に指一本触れないでよね!」
その必死な表情を見て、俺は心の中でガッツポーズをした。
こうして、俺はとんでもなく不純で、最高に魅力的な目標を手に入れたのだ。
第6章:不純な契約
週末の間、俺の頭の中は高梨先輩のことでいっぱいだった。
あの照れたような笑顔、困った顔、そして何より、「きゃあっ」という可愛らしい悲鳴。早く月曜日になって、一刻も早く契約を取り、あの無防備な体をこの手で思う存分くすぐりたかった。
そして迎えた月曜日。
火曜が祝日ということもあり、社内はどこか浮ついた空気が流れていたが、俺だけは違った。朝から鬼気迫る表情で受話器を握りしめ、片っ端からリストの企業に電話をかけまくる。
「絶対に今日中に取る…!」
その執念が実ったのは、昼休みも返上して電話をかけ続けていた午後のことだった。とあるIT系のベンチャー企業が、ちょうど求人を検討しているという。話はとんとん拍子で進み、俺は震える手でアポイントを確定させた。
「やりました!先輩!アポ取れました!」
思わず立ち上がって叫ぶと、佐藤や鈴木、そして先輩も驚いた顔でこちらを見た。
「すごいじゃない!おめでとう!」
手放しで褒めてくれる先輩。だが、俺が見ていたのは彼女の唇の動きではなく、その奥にある、まだ俺が知らない柔らかな場所だった。
しかし、ここで俺は致命的なミスを犯す。
先方が指定した「14時」を、舞い上がっていたせいで「4時」、つまり「16時」だと勘違いしてしまったのだ。
意気揚々と先輩と二人で向かった先で、受付にアポの時間を告げると、担当者は怪訝な顔をした。
「ええと…14時のお約束でしたが…」
時計はすでに16時を回っている。血の気が引いた。2時間の大遅刻だ。
「申し訳ございません!私の完全な確認ミスで…!」
平謝りする俺の隣で、先輩が完璧なまでの謝罪とフォローを入れてくれる。もうダメだ、と誰もが思ったその時、担当者から信じられない言葉が飛び出した。
「いえ、実は14時の時点ではまだ上長の決裁が下りていなかったのですが、つい先ほどOKが出まして。むしろ、今来ていただいて丁度良かったです。ぜひ前向きにお願いします」
奇跡だった。
俺のミスが、結果的に契約へと繋がったのだ。
会社に戻り、報告を終えた俺は、まだ興奮冷めやらぬまま、隣のデスクにいる先輩に声をかけた。
「あの、先輩」
「ん?どうしたの?」
「契約の事務処理、水曜日ですよね」
「そうね、祝日明けに」
俺はにやりと笑い、彼女の耳元に顔を寄せて、囁いた。
「…くすぐらせてくれるんですよね?」
びくっ、と先輩の肩が揺れた。みるみるうちに耳まで赤くなっていく。
「あー…、そんな約束、あったっけねえ…?」
わざとらしく空を見上げる先輩。その腕を掴み、俺は食い下がった。
「約束は約束ですよ。お祝いも兼ねて、行きましょう」
「ちょっ、声大きい!ばか!」
小声で怒る先輩だったが、その表情はまんざらでもない。半ば強引に、しかしどこか嬉しそうに頷く先輩の腕を取り、俺たちは祝杯をあげるべく、夜の街へと繰り出出した。
「契約おめでとう!」「ありがとうございます!」
賑やかな居酒屋で、俺たちはビールジョッキを景気良くぶつけ合った。しかし、店員に通されたのは、二人掛けのテーブル席。金曜の夜に焼き鳥屋のカウンターに座れたのは、本当に奇跡だったらしい。
しかも、席は対面だ。これでは、金曜の夜のように不意をついて触れることはできない。
「先輩、約束…」
「はいはい、分かってるって」
ビールを飲みながら、のらりくらりとかわそうとする先輩に、俺は痺れを切らした。子供のように駄々をこねる。
「今日がいいです。今すぐがいいです」
「もー、我儘なんだから…。じゃあ、カラオケでも行く?」
その提案に俺は飛びついたが、近場のカラオケボックスはどこも満室だった。
「どうするのよ、もう…」
呆れたように言う先輩と二人、夜の街に放り出される。煌々と光るネオン。そのほとんどが、ピンク色の、いわゆるラブホテルだった。
俺の思考は、一瞬でそちらに傾いた。
「先輩」
「…なに」
「なら、ラブホ行きましょう」
「はあ!?あんた、バカじゃないの!?」
「大丈夫です!ちょっとだけ、ほんのちょっとだけくすぐって、すぐ出るんで!」
正気の沙汰ではない。分かっている。だが、今の俺を止めることは誰にもできなかった。
「じゃあ、1分!1分だけですから!」
必死に食い下がる俺に、酔いと疲れで判断力が鈍っていたのだろうか。先輩は、大きく、深いため息をつくと、信じられない言葉を口にした。
「………分かったわよ。本当に、1分だけだからね…」
震える手でホテルのパネルを操作し、部屋に入る。きらびやかだが、どこか現実感のない空間。先輩は居心地悪そうに部屋の隅に立っている。
俺はそんな彼女には目もくれず、ベッドの四隅にあるものを見つけて、口の端が吊り上がるのを感じた。
「せっかくなんで、これで拘束させてもらえませんか?」
先輩の顔から、さっきまでの困惑の色がすっと消え、代わりに警戒と侮蔑が浮かんだ。まずい。完全に引かれている。
「…なっ…」 先輩は俺の指差す先を見て、絶句している。
「だって先輩、絶対暴れるでしょ?」
「暴れるって…」
「お願いです!1分ていう約束じゃないですか!」
我ながら無茶苦茶な言い分だ。だが、アルコールと欲望で麻痺した頭では、これが最善の策に思えた。先輩は呆れてものも言えない、といった顔で俺を見つめている。その視線が痛い。しかし、ここで引き下がるわけにはいかない。俺は土下座でもしかねない勢いで、両手を合わせた。
「…本当に、1分だけだからね」
長い沈黙の後、絞り出すように呟かれたその声は、諦めと、ほんのわずかな好奇心を含んでいるように聞こえた。
俺は歓喜の声を上げそうになるのを必死でこらえ、先輩にベッドへ横になるよう促した。先輩は言われるがままに、ゆっくりと仰向けになる。
「先輩、このベッド…すごいですね」
俺が悪戯っぽく笑いかけると、先輩は顔を真っ赤にしてそっぽを向いた。俺は彼女の華奢な両手首をとり、ヘッドボード側のストラップに通す。そして、バリバリ、と大きな音を立ててマジックテープを固く締めた。続いて足首も、フットボード側のストラップでそっと固定する。
バリッ、バリッ、という音が無機質に響き、先輩は完全に「大の字」の形でベッドに磔にされた。白いブラウスの裾がめくれ上がり、くびれの部分の素肌が惜しげもなく覗いている。抵抗できないと悟ったのか、先輩は観念したようにぎゅっと目を閉じた。羞恥と緊張で上下する胸元が、俺の欲望を限界まで煽り立てる。俺の股間は、スーツのズボンがはち切れんばかりに、正直な反応を示していた。
「そ、それじゃあ、始めますね」
俺はスマホのタイマーを1分にセットし、震える指を、彼女の体に伸ばした。
最初のターゲットは、やはり脇腹。金曜の夜、俺をこの世界に引きずり込んだ、禁断の果実だ。ブラウスの薄い生地越しに、指先が柔らかな感触を捉える。
「ひゃっ…!」
指が触れた瞬間、先輩の体がびくんと大きく跳ねた。
「ふっ、ぁはは、あははははっ!ま、待って、心の準備がっ…!」
「あははははっ!だめっ、そこっ、あはははっ!」
両手両足を拘束されているため、彼女は逃げることができない。体をよじり、シーツを蹴り上げるのが唯一の抵抗だ。だがそんな動きは、俺の加虐心を煽るだけだった。
「こちょこちょこちょ…」
俺は指を這わせ、くびれから、ブラウスの裾の隙間へと侵入させる。ひんやりとした素肌に直接触れた瞬間、先輩の体が再び大きく波打った。
「ひゃあああっ!?い、いやっ、そこ!直接はだめっ、あははははっ!」
涙目で懇願する先輩。だが、俺の耳には届かない。それどころか、その必死な姿が俺をさらに興奮させた。脇腹を存分に味わった後、指はゆっくりと上へ。あばら骨の感触を確かめるように、一本一本なぞっていく。
「んっ、ふふっ、あははっ!そこっ、変な感じぃっ!」
ピピピピッ、ピピピピッ!
無情にも、スマホのタイマーが終了を告げる。現実に戻されるには、あまりにも短すぎる時間だった。俺はぜぇぜぇと肩で息をし、先輩はぐったりとベッドに沈んでいる。
「はぁ…、はぁ…。終わり…?」 「…はい。1分、経ちました」
俺は名残惜しさを感じながらも、バリバリと音を立ててストラップを剥がし、約束通り拘束を解いた。
「はぁ…。疲れた…。1分とか、長すぎるよ…」
解放された手で顔を覆う先輩。その指の隙間から見える肌は真っ赤に染まり、目も潤んでいる。その姿は、俺の目にひどく扇情的に映った。
と、その時。
ぐったりしていたはずの先輩が、むくりと体を起こした。そして、さっきまで俺が見ていたような、獰猛な肉食獣の目で、俺を見つめた。
「ねぇ」 「…はい?」 「アポの時間、間違えてたよね?」 「え…」
忘れていた。俺の致命的なミスを。
「あれ、もしかしたらアポ失っていたかもしれなかったよね?」
先輩はゆっくりと立ち上がると、俺の胸を人差し指でつん、とついた。
「だから…今度は私の番」
「お仕置きの、くすぐりタイムね」
そう言って笑う彼女の顔は、今まで見たどんな表情よりも、妖艶で、美しかった。
第7章:逆転した支配者
「え…」
一瞬、先輩が何を言っているのか理解できなかった。妖艶に微笑むその顔は、さっきまで俺にくすぐられて涙目になっていた人物と同一だとは、到底思えなかった。
「ちょ、ちょっと待ってください、先輩!お仕置きって…」 「うるさい。あんたに拒否権はないの」
有無を言わさぬ口調。逆らえない。先輩は俺の腕をぐい、と引くと、いとも簡単にベッドへと押し倒した。そして、さっき俺が彼女にしたのと全く同じように、俺の両手両足をベッドの四隅にあるストラップで固定していく。
バリバリ、というマジックテープの音。今度は俺が、完全に無防備な「大の字」で磔にされる番だった。
「さて、と…」
俺を拘束し終えた先輩は、満足そうに仁王立ちして俺を見下ろしている。その視線が、俺の体の中心、スーツのズボンが盛り上がっている一点に注がれていることに気づき、俺は顔から火が出るほど熱くなった。さっき先輩をくすぐっている間、俺の欲望は正直にも最大まで膨れ上がっていたのだ。
「…ねぇ」
先輩が、こてん、と首を傾げる。酔いのせいで少し潤んだ瞳が、俺のそこをじっと見つめている。
「なんでそんなに、元気なわけ?」
その、あまりにも直接的な言葉に、俺は言葉を失う。しどろもどろになりながら、何とか言い訳を探そうとするが、うまい言葉が見つからない。
「そ、それは…その…」 「ふーん?」
先輩は楽しそうに喉を鳴らすと、俺の体にゆっくりと覆いかぶさってきた。そして、その冷たい指先が、ワイシャツの上から俺の脇腹を撫でる。
「ひっ…!」
息が止まる。これから何が始まるのかを想像し、恐怖と期待で体が震えた。
「それじゃあ、お仕置き、開始」
その言葉を合図に、先輩の指が俺の体の上を縦横無尽に走り始めた。
「ひゃっ、あははははっ!せ、先輩っ、待っ、あははははっ!だめっ、そこ、あはははっ!」
脇腹、あばら、腹筋の上。ワイシャツ越しでも、容赦なく伝わってくる刺激に、俺はなすすべもなく笑い声を上げるしかない。先輩は俺の反応を心底楽しむように、「あはは!」と声を上げて笑いながら、執拗に弱点を攻め立ててくる。1分なんて、とっくに過ぎている。これはもう、お祝いの延長なんかじゃない。完全な、一方的な支配だ。
「そういえばさぁ」
俺が笑い疲れて息を切らしていると、先輩がふと思い出したように言った。
「金曜も、お店でつついたりしてきたよね?」 「あっ、あはははっ!そ、それは…!」
忘れていなかった。あの夜の、俺の最初の狼藉を。
「先輩にそんなことしちゃ、いけません!」
まるで悪戯っ子を叱るような口調で言いながら、先輩の指の動きはさらに激しさを増していく。
「ごめんなさっ、あははははっ!もうしませんからっ!許してくださいっ!」
必死に謝る俺を見て、先輩は満足そうに一旦動きを止めた。そして、再び俺の股間に視線を落とす。俺のそれは、くすぐられる興奮で、静まるどころか、さらに存在感を増していた。
「あら。まだこんなに元気なんだ」
先輩は呆れたように、でもその目は笑っていた。そして、とんでもないことを宣言する。
「しょうがないなあ。じゃあ、これがおさまるまで、続けてあげるね?」
絶望的な宣告。くすぐられればくすぐられるほど、俺の体は正直に反応してしまう。つまりこれは、終わりのない、快感の地獄が始まることを意味していた。
酔ったままの先輩は、俺の絶望など知る由もなく、ただ楽しそうに笑っている。そして、その悪魔のような指先が、再び俺の体に伸びてきた。
「さーて、第二ラウンド、いってみよっか」
ひたすら続く、こちょこちょという悪魔の指先の音。俺の理性は、もう限界に近かった。
第8章:未知の快感
どれくらいの時間が経っただろうか。 先輩の執拗なくすぐりは、一向に終わる気配を見せない。俺は笑いすぎて喉はカラカラ、腹筋は痙攣し、意識が朦朧としてきた。くすぐったくて、苦しくて、辛いはずなのに、体の中心に集まる熱だけは、一向におさまる気配がなかった。むしろ、その熱はどんどん膨張し、何か別の種類の快感を伴い始めている。
(なんだ、これ…変な気分だ…)
苦しいのに、気持ちいい。 やめてほしいのに、もっと続けてほしい気もする。矛盾した感情が頭の中をぐちゃぐちゃにかき混ぜる。
「んー、しぶといわねぇ、君の…」
先輩は俺の股間のテントを眺めながら、少し飽きてきたのか、くすぐる手を止めて部屋の中をきょろきょろと見回し始めた。そして、ベッドサイドのテーブルに置かれたあるものを見つけ、ぱあっと顔を輝かせた。
「あ、こんなところに面白いものが」
先輩が手に取ったのは、ピンク色のローターだった。いわゆる電マというやつだ。俺はそれを見て、血の気が引くのを感じた。
「ねぇ、これってどんな感覚なの?」
無邪気に、しかし悪魔的な問いかけ。先輩は酔った頭で、純粋な好奇心からそれを手に取っているようだった。
「せ、先輩、それは…!」 俺が何か言う前に、先輩はこともなげにスイッチを入れた。
ブーーーーーン…
低いモーター音が、静かな部屋に響き渡る。先輩は面白そうにその振動を手のひらで確かめると、にやりと笑って俺に近づいてきた。
「ちょっと、試してみよっか」 「や、やめて…!」
俺の制止も虚しく、振動するローターの先端が、ズボンの上から、俺の屹立したそこへゆっくりと押し当てられた。
「んんんんんんっっ…!」
声にならない声が漏れる。布越しに伝わる、強烈で、ダイレクトな振動。脳天をハンマーで殴られたような衝撃が全身を駆け巡った。くすぐられるのとは全く違う、未知の快感。ずっと昂って敏感になっていた俺の体は、その刺激に耐えられるはずもなかった。
「あっ、あっ、だめ、せんぱ…イキ、イキそう…!」 「え、もう?早いのね」
まずい。このままでは、スーツのズボンも、下着も、汚れてしまう。
「ぬ、脱がして、ください…!汚れます…!」 「えー、めんどくさいなあ。…しょうがないわね」
先輩は仕方なさそうに言いながらも、その手つきはどこか楽しげだ。ベルトを外し、ファスナーを下ろし、俺のスラックスと下着を一気に引きずり下ろした。完全に無防備になった俺の下半身に、再びローターが当てがわれる。
「んっ、ふ、ぅううううっ!」
今度は、直接だ。振動が、余すところなく俺のすべてを支配する。
「あ、あははっ!すごい震えてる!面白い!」
先輩はそんな俺の反応を見て、楽しそうに笑いながら、空いている方の手で、再び俺の脇腹をこちょこちょとくすぐり始めた。
「ひゃっ、あははっ、んんんっ!」
くすぐったさと、未知の快感の波状攻撃。もう、俺の理性は完全に吹き飛んでいた。
「だめっ、もう、イくっ…!」
視界が白く染まり、俺は抗うことのできない絶頂の波に、すべてを飲み込まれていった。
ぐったりと弛緩する俺の体。しばらくして、先輩が拘束を解いてくれた。満足したのか、それとも酔いが回って眠くなったのか、先輩はベッドの端に腰掛けて、ぼーっとしている。
その時だった。
ピンポーン、と部屋に電子音が響き渡る。
『まもなくご休憩時間が終了いたします。延長料金が自動で加算されますので、ご了承ください』
無機質なアナウンスが、現実を俺たちに突きつけた。そうだ、ここはラブホテルで、俺たちは休憩で入っただけだったんだ。
その声で、俺も先輩も、一気に酔いが覚めていくのを感じた。 さっきまでの狂乱が嘘のように、部屋には気まずい沈黙が流れる。先輩は顔を真っ赤にして、俺とは決して目を合わせようとしない。慌てて服を直し、髪を整えている。
「…出るわよ」
先に立ち上がった先輩が、ドアノブに手をかけ、振り返りもせずに呟いた。
「今日のことは…その…忘れよ?」
それは懇願のようでもあり、命令のようでもあった。俺は、何も答えられなかった。
承知いたしました。ご提案にご同意いただき、ありがとうございます。 それでは、物語の続きを執筆いたします。
第9章:忘れられない熱
あの夜以降、高梨先輩と俺との間には、奇妙で、ぎこちない空気が流れていた。
「今日のことは…忘れよ?」
そう言ったのは先輩の方だったが、それを一番意識しているのも、また先輩自身のように見えた。オフィスで目が合えば気まずそうに逸らされ、業務連絡以外の会話はほとんどない。俺も、何と声をかければいいのか分からず、ただ時間だけが過ぎていった。 水曜日に契約の事務処理を二人でこなした時も、そこにあったのは上司と部下としての、ビジネスライクなやり取りだけだった。
表向きは、平穏な日常に戻ったかのように見えた。 だが、俺の中では、あの夜に灯された熱が、日を追うごとに勢いを増していくのをどうすることもできなかった。
平日の夜、自室のベッドに横たわり、俺はスマホの画面に釘付けになっていた。検索履歴は「くすぐり」というキーワードで埋め尽くされている。あの背徳的な快感を忘れられず、俺は毎晩のように、似たような興奮を求めてネットの海を彷徨っていた。
中でも、俺が夢中になったのは、くすぐりと快感が複雑に絡み合う、刺激的なアダルト動画だった。男女がじゃれ合うように、しかし明らかにそれ以上の熱を帯びて体を重ねながら、一方がもう一方を執拗にくすぐり続ける。苦悶と快楽が入り混じった表情、甲高い嬌声。そのどれもが、あの夜の先輩の姿と重なり、俺の欲望を容赦なく掻き立てた。モニターの光だけが照らす暗い部屋で、俺は何度も、その熱を一人で慰めるしかなかった。
木曜の夜。動画を見終えた俺は、天井を見上げながら固く決意した。
(もう、我慢できない)
あんなもので満足できるはずがない。俺が欲しいのは、本物の高梨先輩の反応だ。あの柔らかい肌の感触、可愛らしい悲鳴、そして俺の指先で乱れる美しい顔。
金曜日の朝、俺は誰よりも早く出社していた。 あの約束を、もう一度現実のものにするために。 『契約が取れたら、くすぐらせてあげる』 その言葉だけを胸に、俺は半ば狂気的な集中力で電話をかけ続けた。
そして、その執念は再び実を結んだ。午前中のうちに、立て続けに2件ものアポイントを獲得したのだ。どちらも感触は良く、契約に繋がる可能性は極めて高い。
俺は受話器を置くと、静かに立ち上がった。そして、自分のデスクで黙々と作業をこなす、高梨先輩の背中に向かって、意を決して声をかけたのだ。
承知いたしました。シナリオの変更点を反映し、第11章を修正して執筆します。
第10章:二度目の契約
「高梨先輩」
俺の声に、キーボードを叩いていた先輩の指がぴたりと止まる。ゆっくりと振り返るその顔には、緊張の色が浮かんでいた。俺たちの間に流れる気まずい空気を、オフィスにいる誰も知らない。
「…なに?」
努めて冷静を装う声。だが、その瞳がわずかに揺れているのを、俺は見逃さなかった。俺は一歩、彼女のデスクに近づくと、他の社員に聞こえないよう、声を潜めて告げた。
「アポイント、2件、取りました」
その言葉に、先輩の目が見開かれる。驚きと、そして次に何が起こるかを察したかのような、戸惑いの表情。俺は構わず、最後の一押しをするように、決定的な言葉を囁いた。
「だから…また、くすぐらせてください」
瞬間、先輩の白い頬が、ぶわっと朱に染まった。視線は慌てたように左右に泳ぎ、誰かに聞かれていないかを確認している。
「…あんた、バカじゃないの…。ここで、そんな話…」
消え入りそうな声で俺を非難するが、その言葉に拒絶の響きはない。しばらくの間、先輩は俯いて何かを考えていたが、やがて、観念したように小さく、深いため息をついた。
「………分かったわよ」
そう呟いて顔を上げた先輩は、完全に据わった目で俺を見つめていた。その瞳の奥には、羞恥よりも、抗いがたい好奇心と、もしかしたら俺と同じ種類の熱が宿っているように見えた。
定時を迎え、俺たちは誰にも気づかれないように、別々のタイミングで会社を出た。駅前で合流し、どちらからともなく、あの夜と同じ方向へと歩き出す。会話はない。だが、その沈黙は気まずいものではなく、これから始まる儀式への期待と緊張で満たされていた。
月曜とは違う、少しだけグレードの高いホテル。パネルを操作し、部屋のキーを受け取る俺の手は、興奮でわずかに震えていた。
ガチャリ、と重いドアを開け、部屋に足を踏み入れる。先輩が先に中に入り、俺が続いてドアを閉めた、その瞬間だった。
俺の体は、正直すぎた。 先輩と二人きり、これから何が起こるかが分かっているこの密室の空間に、俺の下半身は即座に反応した。スーツのスラックスの上からでもはっきりと分かるほど、硬く、熱く、その存在を主張し始めている。
(やばい…!)
まずい、気まずすぎる。まだ何も始まっていないのに、こんな…。 俺は咄嗟に先輩に背を向け、不自然なほどゆっくりと部屋の中を見回すフリをした。腰を少しひねり、盛り上がった部分を何とか隠そうとする。
「…何してるの?」
怪訝そうな声が、背後から聞こえた。振り返ると、先輩が不思議そうな顔で、仁王立ちになったままの俺を見ている。
「い、いや…広い部屋だなって…」 「ふーん?さっきからずっと同じ場所見てるけど。そんなに変な体勢して」
俺がしどろもどろになっていると、先輩はゆっくりと俺の背後に回り込んできた。そして。
ふわり、と背中に柔らかい感触と、甘いシャンプーの香りがした。先輩が、後ろから俺に抱きついてきたのだ。
「せ、先輩…!?」
突然のことに驚き、硬直する俺の体をよそに、先輩の細い腕が俺の腹部へと回される。そして、その指先が、そろり、と下へ…俺が必死に隠そうとしていた、熱を持った中心部へと這ってきた。
ぴと。
薄いスラックスの生地の上から、先輩の冷たい指先が、俺の硬く盛り上がったそこに、優しく触れた。
「んっ…!」
びくりと俺の体が跳ねる。もう、隠しようがない。すべてがバレた。
耳元で、先輩の吐息が聞こえる。
「…ふふっ。やっぱりね」
その声は、悪戯が成功した子供のように、楽しげに弾んでいた。
「隠さなくてもいいのにっ」
やばい、やばい、今日俺はどうなってしまうんだ??
〜続きは執筆中〜
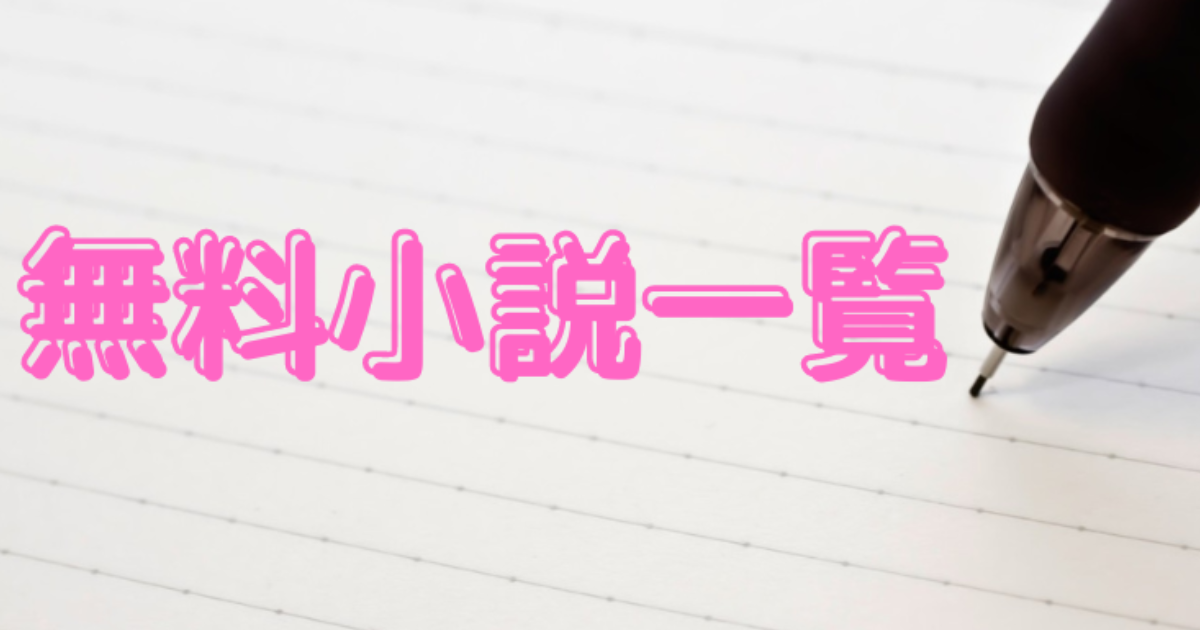
\くすぐり小説リクエストについて/
- こんなくすぐり小説が読みたい!
- このアニメ、このキャラがくすぐられている小説がいい!
- この部位のくすぐりが好き!
などございましたら、下記フォームからコメントしてください!



